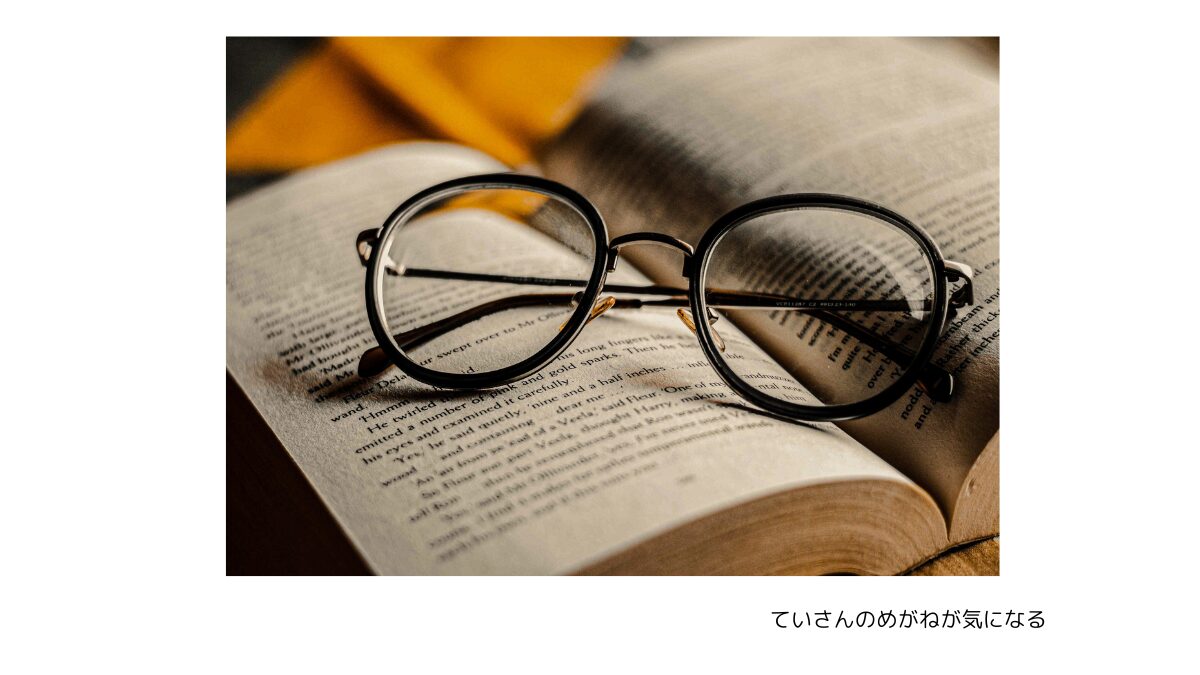NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で話題沸騰中のキャラクター「てい」
橋本愛さん演じる、着物に黒縁メガネ姿のインパクトは強烈ですね
今回は、「てい」のメガネの秘密や蔦重との関係、史実との違いなど、気になるポイントを徹底解説します
ていの“黒縁メガネ”は江戸時代にも実在したのか?
江戸時代にも黒縁メガネのような眼鏡は実在していました
日本に眼鏡が伝来したのは室町時代中期(15世紀頃)で
江戸時代に入ると国内での製造も始まり、知識人や商人を中心に眼鏡の使用が広がりました
江戸時代中期から後期にかけては、出版文化の発展や識字率の上昇とともに
読書用として眼鏡の需要が増加。真鍮や木製のフレームにレンズをはめたシンプルな構造で
丸型のデザインも多く見られました
浮世絵にも、ていがかけているような丸くて黒縁の眼鏡をかけた人物が描かれており
史料に基づいた演出と考えられます
ただし、現代のように鼻あてやテンプル(つる)が発達したものは少なく
鼻に引っかけたり紐で耳にかけたりするタイプが主流でした
それでも、ドラマ「べらぼう」のていの黒縁メガネは
当時の実物や浮世絵の描写にかなり近いリアルな再現といえます
べらぼうのてい 蔦重からのストレートすぎるプロポーズ、その理由
蔦重の“ストレートすぎるプロポーズ”は、ていの心にまっすぐ向き合い
彼女の本質をしっかりと見ていたからこそ生まれたものでした
蔦重は、ていが自分に自信を持てず「自分のような石頭のつまらない女には務まらない」と思い悩み
家を出てしまった際、彼女を引き止める場面で真摯な想いを伝えます
「『出会っちまった』って思ったんでさ」
「俺と同じ考えで、同じつらさを味わってきた人がいたって」
「この人なら、この先、山があって谷があっても、一緒に歩いてくれんじゃねえか、いや…一緒に歩きてえって」
「おていさんは、俺が、俺のためだけに目利きした、俺のたった一人の女房でさ」
このプロポーズがストレートだった理由は
蔦重が「本に対する想い」や「苦労を共にしてきた感覚」をていと分かち合い
彼女を唯一無二のパートナーと認めていたからです
蔦重にとって、ていは単なるビジネスパートナーではなく
人生を共に歩む「たった一人の女房」として選び抜いた存在でした
視聴者からも「最高のプロポーズ」「5億年ぶりにときめいた」と絶賛されるほど
蔦重の“火の玉ストレート”な想いは、多くの共感を呼びました
ていと蔦重はなぜ結婚した?二人の絆の背景
ていと蔦重が結婚した理由、そして二人の絆の背景には
価値観の一致と実務的なパートナーシップが大きく関わっています
- ていは「江戸の本屋の娘」として育ち、小さい頃から本や出版文化に親しんできた女性です。彼女は本を「商売」としてだけでなく、「文化」としての意味も深く理解していました。
- 蔦重もまた、「読み手の心に火をつけるような本を届けたい」という強い信念を持っており、ていと蔦重は「本を通して世の中を照らしたい」という精神的な軸で深く共鳴していました。
- ドラマの中で、ていは一度は出家を考えますが、蔦重が「力を合わせればいい店ができる」と誠実に説得し、ていも「商いのためだけの夫婦」という条件で結婚を受け入れます。
- この「商いのためだけの夫婦」という形は、恋愛感情だけでなく、互いの能力や信念を尊重し合う“ビジネスパートナー”としての信頼関係を象徴しています。
つまり、二人は「本」という共通の情熱を持ち、互いの強みを認め合った結果
人生と商いを共にするパートナーとして結ばれたのです
恋愛だけでなく、価値観と目的の一致が、二人の強い絆の背景にありました
ていは実在した人物?史実とドラマの違い
「てい」はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に登場するキャラクターで
実在した人物かどうかは明確な史料がありません
ドラマでは蔦屋重三郎の妻として重要な役割を担っていますが
史実として「てい」という名や人物像は伝わっていません
- ドラマの設定では、「てい」は江戸の本屋の娘として育ち、本に囲まれた知性派の女性という背景が与えられています。
- 史実の蔦屋重三郎にも妻がいたことは確かですが、名前や詳細な人物像は残されておらず、小説や映画では「トヨ」とされることもあります。
- 「てい」という名前や性格、エピソードはドラマのオリジナル設定です。
- ドラマの中で描かれる、蔦重とていの関係や性格の違い、そして「本を愛する」という共通点で結ばれるというストーリーは、創作要素が強いものです。
まとめると、「てい」は史実の蔦屋重三郎の妻をモデルにしつつも
名前や人物像は創作であり、史実とは異なる部分が多いキャラクターのようです
べらぼうのていと蔦重 「商いのためだけの夫婦」の真相
「商いのためだけの夫婦」という蔦重とていの関係は
恋愛感情だけでなく、仕事・価値観を共有するパートナーシップに重きを置いたものでした
ドラマ『べらぼう』で描かれる二人は、性格や生い立ちは異なりますが
「本を愛し、出版を通じて世の中を照らしたい」という精神的な軸が一致していました
ていは江戸の本屋の娘として、本に囲まれて育ち、その知性や価値観の中心に「本」がありました
蔦重もまた、単なる商売ではなく文化的意義を重視し、出版活動に情熱を注いでいました
劇中でていは一度出家を決意しますが、蔦重が「力を合わせればいい店ができる」と説得し
ていも「商いのためだけの夫婦」という条件で結婚を受け入れます
蔦重自身も「いろいろあって、もう男はこりごりらしいんでさ」と語っており
恋愛や家庭よりも、互いの能力や信念を尊重し合うビジネスパートナーとしての関係を選んだことがわかります
史実では、蔦重の妻について詳細な記録は残っていませんが
本屋の娘として夫を支えた存在だったことは伝わっています
ドラマの「商いのためだけの夫婦」という設定は
史実の「仕事を通じて結ばれたパートナーシップ」を現代的に分かりやすく表現したものです
つまり、二人の本当の関係は
「互いの強みや価値観を認め合い、商い=人生を共に切り拓く同志」としての結びつきが核心にありました
べらぼうのてい まとめ
NHK大河ドラマ『べらぼう』のていは、史実では名が残っていませんが
蔦屋重三郎の妻として「本を通じて世の中を照らしたい」と願う知性派の女性として描かれています
二人は価値観を共有し、「商いのためだけの夫婦」として互いをパートナーと認め合い
人生を共に歩みました
これからの二人の関係を見守っていきましょう