北海道ニセコ町で進行していた「ラ プルーム ニセコリゾート」の開発が
2024年秋ごろから建設中断、2025年4月には運営会社の破産手続き開始という事態に発展しました
この出来事は、ニセコの未来や地元住民、日本人観光客にとって大きな不安材料となっています
本記事では、問題点を整理し、地元や日本人が抱える悩み・疑問を解決する視点から解説します
1. ラプルームニセコ中断の経緯と背景
- 2020年、香港系などアジア資本により設立された「La plume Niseko Resort」特定目的会社が、219室と5つのヴィラからなる高級リゾートの建設を開始
- ニセコはインバウンド需要や円安を背景に「ニセコバブル」と呼ばれるほどの観光開発ラッシュが続いていました
- しかし、資金繰りの悪化や建設会社への未払いが発生し、2024年秋には工事がストップ。2025年4月、建設会社から破産申立てがなされ、開発会社は破産手続き開始となりました
- 建物は基礎や骨組みができた状態で放置され、今後の見通しは不透明です
2. 問題点の整理
資金調達・経営の脆弱性
- 外資主導のプロジェクトは、資金繰りや経営判断が地域事情と乖離しやすい。
- 建設会社への未払いなど、地元企業への影響も深刻
景観・環境への影響
- 建設途中で放置された建物が景観を損ね、観光地としての魅力低下を招く懸念
- 開発ラッシュによる環境負荷やインフラへの影響も指摘されています
地元経済・雇用への波及
- 開業を見込んでいた地元の雇用創出や経済波及効果が消失
- 既存の宿泊・飲食業者も、期待していた来客増が見込めなくなる恐れ
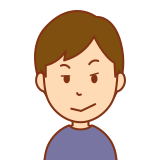
北海道、中国資本がかなり入っているから結構マズい状況なんじゃ…
3. 地元民・日本人観光客の悩み・疑問とその解決策
Q1. 「工事中断で町の景観が悪くなった。どうなるの?」
- 放置建築物は景観悪化や治安面での不安を生みます。今後、破産管財人による資産整理が進み、土地・建物の新たな活用方法が模索される見込みです。地元自治体や住民が積極的に意見を出し、再開発や撤去を働きかけることが重要です
Q2. 「地元経済や雇用への影響は?」
- 大型リゾートの中断で、雇用や経済効果の消失が懸念されます。地元企業や自治体は、既存の観光資源の磨き上げや、多様な宿泊・体験型観光の推進など、リスク分散型の観光戦略が求められます
Q3. 「外資系リゾート開発は本当に地域のためになるのか?」
- ニセコでは近年、外資系による開発が急増し、地元住民の生活や文化との摩擦も発生しています。資本の流入による経済効果と、地域社会への配慮のバランスが課題です。今後は、地元自治体が開発規制や地域貢献を求めるルール作りを進める必要があります
Q4. 「観光バブルの副作用は?」
オーバーツーリズムによる地元住民の生活環境悪化や、物価・不動産価格の高騰、文化摩擦などが既に顕在化しています
観光客向けと地元民向けのサービス・空間の分離や、観光客へのマナー啓発が必要です
4. 今後の展望と地域が取るべきアクション
- 破産処理後の土地・建物の利活用:地元自治体や住民が主導し、地域に根ざした再開発案を検討することが望まれます。
- 観光と生活の共存:観光客・外資誘致に頼りきりにならず、地元住民の生活の質を守る施策(住宅確保、インフラ整備、環境保全)を強化する必要があります
- 持続可能な観光への転換:短期的なバブルに依存せず、地域資源を活かした持続可能な観光戦略への転換が求められます
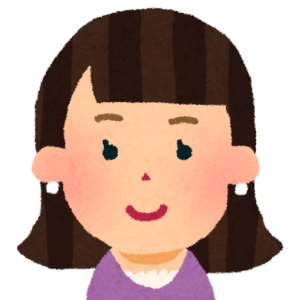
外資流入は地域経済にとってチャンスでもありますが
過度に依存すれば資本の引き潮で一気に構造リスクが顕在化しますね
まとめ
ラプルームニセコの中断は、外資系リゾート開発のリスクや
観光バブルの副作用を浮き彫りにしました
地元民や日本人観光客が安心して暮らし・訪れるためには
地域主導のガバナンス強化と、観光と生活のバランスを取る新たな仕組み作りが不可欠です
今こそ、地元の声を反映した持続可能なニセコの未来像を描く時です
ガバナンス(governance)とは、英語で「統治」や「統制」、「管理」を意味する言葉です。 組織が目的を達成し、長期的に維持・発展するためには
意思決定を監督・評価する体制が必要です。 ガバナンスは、組織活動を制御するための統治行動・支配行動を指しています


